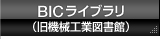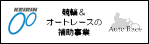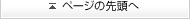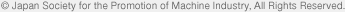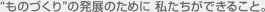研究会・イベントのご報告 詳細
「AI・DX時代のロボット開発を考える」
| 主催:(一財)機械振興協会経済研究所主催 第486回機振協セミナー「AI・DX時代のロボット開発を考える」開催報告 オンデマンド配信あり | |
|---|---|
| 開催日時 | 2025年6月27日(金)14:00~15:30 |
| 場所 | WEBシステムにより開催(Zoom) |
| テーマ | 「AI・DX時代のロボット開発を考える」 |
| 講師 | 講師:立命館グローバル・イノベーション研究機構 機構長代理 特別招聘研究教授 株式会社チトセロボティクス 取締役副社長 川村 貞夫氏 モデレータ:機械振興協会経済研究所 調査研究部 研究副主幹 森 直子 |
| 内容 |
2025年6月27日(金)にWebシステムより、第486回機振協セミナー「AI・DX時代のロボット開発を考える」を開催しました。講師は、立命館グローバル・イノベーション研究機構機構長代理特別招聘研究教授・株式会社チトセロボティクス取締役副社長の川村 貞夫氏にお願いしました。またモデレーターおよび調査研究事業の概要説明は機械振興協会経済研究所調査研究部研究副主幹の森直子が務めました。当日は、104名にオンラインでご参加いただきました。ご参加いただきました皆様に、厚く御礼申し上げます。【講演内容】本講演では、深刻な人手不足が問題となっている「ノンデスクワーカー」の支援に向けて、AIを適切に活用しながらロボット開発をさらに促進すべきであるという研究会の提案と、サービスロボットの現状に関する報告が行われた。本講演の冒頭では、調査研究委員会の概要に関して、モデレーターの森直子が説明を行った。 現在、いわゆる「第4次ロボットブーム」とも言われるように、ロボット活用は急速に進展している。その背景には、ニューラルネットワーク型AI技術の発展があり、これをロボットに応用することで、より高度な知能化が進められている点が挙げられる。また、サイバー空間を活用したネットワーク接続によるロボット制御への注目も高まっており、それに伴い開発投資も活発化している。しかしながら、AIやサイバー空間ネットワーク接続への関心が過度に集中する一方で、現場の最前線で求められる物理的な自動化技術の開発が停滞しているのではないか。このような問題意識から、本研究会では、『ノンデスクワーカー支援のためのAI利用ロボット開発の指針―ロボット側から考える―』を取りまとめ、ロボット開発推進のための6つの指針を提案した。 続いて、講師の川村貞夫氏が登壇し、「急速なAI技術発展のなかでのロボット開発の課題と現状」をテーマに、研究会での議論と自身のロボット研究及び会社での取り組みを踏まえた講演を行った。 講演の冒頭では、人工知能とロボット開発に対する誤解が存在することが指摘された。特に、「AI=高度なロボット」という誤った認識が広まっている現状に対し、映画『ターミネーター』を例に挙げながら、知能のみでは高度なロボットは実現できないことが説明された。 ロボットとは、センサ、コンピュータ、アクチュエーター(駆動部)、エネルギー源、構成材料など複数の要素が統合されたシステムであり、これらを総合的に理解し設計することの重要性が強調された。また、人間の運動制御の複雑さについても言及し、一見簡単に見える人間の動作が、実際には精密で高度なメカニズムに基づいていることが、脳の階層構造や無意識的な運動制御の巧妙さなどの科学的知見を交えながら解説された。 さらに、AI技術、特に機械学習に関しては、現状の課題に対して批判的な見解を示された。具体的には、データ収集の困難さ、高コスト、シミュレーションと現実とのギャップ、膨大な計算量とリアルタイム処理とのトレードオフ、出力結果の解釈の難しさなどといった問題点が挙げられ、現時点では機械学習はロボット開発に完全に適しているとは言えないという見解が示された。 一方で、近年急速に進展している大規模言語モデル(LLM)や視覚言語モデル(VLM)については、自然言語処理や画像理解の分野で著しく進歩を遂げていることが認められた。ただし、それらを産業ロボットへの応用する際には、誤動作リスク、推論と計画のとのギャップ、センサとの統合の難しさ、データの非効率性といった、依然として多くの課題が残されていることも指摘された。特に、産業用ロボットでは、高剛性、高速性、高精度な繰り返し動作といった特徴があり、こうした従来型のロボットシステムと最新のAI技術をどのように融合させるかが今後の技術開発における重要な課題であると強調された。 講演の最後には、川村氏の研究グループでの取り組みも紹介された。上述の課題を踏まえ、AIだけでロボットを完全に制御することは難しいとういう前提のもと、同グループでは、AIとロボットコントローラーを組み合わせた制御方法を採用している。具体的には、AIの役割をユーザーの指示からプログラムを生成する部分に限定することで、現実的な制御を実現している。今後は、複数の単純な問題解決手法を組み合わせることで、より高度なロボットシステムの構築を目指している。 講演後は質疑応答が行われ、川村貞夫氏の講演された新システムの経済性やAIを搭載したロボットの処理速度に関する質問の他、AIを使わなくても対応できる分野ではあえてAIを搭載しないロボットの方が望ましいのではないかといった視点からも議論が行われ、本公演は盛況のうちに終了した。 ※解像度は画面右下の[360P]をクリックして高画質等にご調整ください。 このセミナーの資料はこちら↓からご覧になれます。 【セミナー資料①】 【セミナー資料②】 |